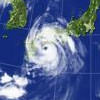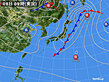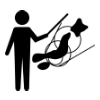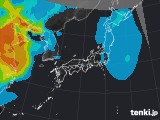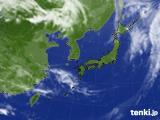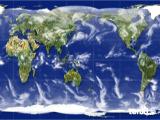では、乾燥注意報はどのような基準で発表されるのでしょうか。
乾燥注意報の発表基準は、「空気がどれくらい乾燥しているか(=最小湿度)」と、「木材がどれだけ乾燥しているか(=実効湿度)」の2つを主な目安にしています。
<最小湿度>1日の中で最も低い相対湿度(※)のこと。
晴天時には、最高気温が観測される昼過ぎに最小湿度が観測されることが多くなっています。
<実効湿度>数日前からの相対湿度(※)を考慮した、木材の乾燥の度合い。
一時的に湿度が変化しても、木材の内部まで急に乾燥したり、湿ったりはしないので、そのことを考慮したのが「実効湿度」です。とくに、実効湿度が60〜50%以下になると火災の件数が増えるとされています。
(※相対湿度とは、普段私たちが「湿度」と呼んでいるもので、ある温度において空気が含むことができる最大の水蒸気量に対して、実際に含まれている水蒸気量がどれくらいかを比率で表したもの。)
なお、具体的な基準の数値は、地域によって異なります。
例えば、東京都(島しょ部を除く)では最小湿度25%・実効湿度50%、新潟県では最小湿度40%・実効湿度65%、大阪府では最小湿度40%・実効湿度60%、沖縄県では最小湿度50%・実効湿度60%です。
また基準に風速が加わる地域もあり、宮城県では最小湿度45%・実効湿度65%で風速7m/s以上または最小湿度35%・実効湿度60%となっています。
その他、各地域の乾燥注意報の発表基準は、気象庁HPで確認することができます。
→気象庁「警報・注意報発表基準一覧表」(外部リンク)